「おもしろい本」を見つける「読書法」【第5回】
ちまたにはさまざまなブックレビューであふれています。
そんななか存在する「作家が書いた書評集」。
プロフェッショナルが語る「本音」が読める貴重なものです。
心の奥に響く本音のレビューを読む「たのしみ」。
また、そこで取り上げられた本自体の「おもしろさ」。
それらには格別な味わいがあると感じています。
恩田陸『土曜日は灰色の馬』から植草甚一について

〈目次〉
気がつくとそばにいた偉大な「J・Jおじさん」

『雨降りだからミステリーでも勉強しよう』(植草甚一著 ちくま文庫)
「ものごころついた頃から植草甚一は既に存在していた。彼のセピア色の世界が、古い地図みたいに最初からそこにあったのだ。」
こんな書き出しで始まるのが、恩田陸の書評「『雨降りだからミステリーでも勉強しよう』を再読する 植草甚一について」です。
冒頭で、「小学校五年生のときに本屋で買ったことを覚えている」「私を捉えたタイトルとデザイン」というのですから、なんとも ”おませな” 読書マニアぶりには驚かされます。
小学生でもう植草甚一なんかを読んでいるのですからね。
のちにミステリー作家としてデビューするのにも納得してしまいます。
植草甚一といえば、映画会社・東宝に勤務後、40歳の頃から映画評論や音楽評論(ジャズ)を書き始め、1960~1970年代にかけて、映画、モダンジャズ、ロック、海外ミステリー小説など、幅広いジャンルで日本にサブカルチャーを広めた第一人者的存在です。
映画評を単行本として発刊する際に、語呂がいいとして自らのニックネームを「J・J」としたということです。
「植草甚一は、気がつくともうJ・Jおじさんだった。笠智衆がいつも映画の中ではおじいさんだったように。」
というように、1964年生まれの恩田陸にとって、また、当時の多くの若者たちにとって、1908年生まれの「J・J」は、欧米、特にアメリカでその時々に流行っている映画、音楽、本など、楽しいポップカルチャーをいち早く教えてくれる、信頼と親しみの持てる「おじさん」的存在だったのです。
そんな感じの「おじさん」ですから、植草甚一に影響を受けたクリエイターは枚挙にいとまがありません。
また、彼の代表的な著書『植草甚一スクラップブック』を再編集した書籍『植草甚一研究』(晶文社刊)には、池波正太郎、浅井慎平、片岡義男、小林信彦、田村隆一、筒井康隆、虫明亜呂無、淀川長治ら、たくさんの著名人が文章を寄せています。
ちなみに、植草の死後、「植草甚一コレクション」とでも呼ぶべき4,000枚を超える大量のジャズのレコード・コレクションの行方がはたしてどうなるのか、ちまたで話題になったことがありました。
結局、早稲田大学在学時代は「ジャズ研」でトランペットを吹いていたというほどのジャズファンであるタレントのタモリがすべて買い取って、植草甚一コレクションを引き継ぎました。
恩田陸が「いったい何度読んだか分からないけれど」という植草甚一の名著『雨降りだからミステリーでも勉強しよう』を久しぶりに読んで、いとしの「J・Jおじさん」について論じます。
しかし、「何度読んだか分からない」って、すごいことですね。
みなさんには、何度読んだか分からない愛読書、ありますか?
伝説的ブックガイドへの「イジリ」と「ツッコミ」
前回紹介した松本清張に対する評論からは、作家・恩田陸として、清張への「畏敬の念」や、より複雑化する現代社会と対峙するがゆえの緊張感や危機感が感じられてました。
それとはがらり一変、ここでの文章には明らかに、心からはしゃいでいるような楽しさが感じられます。
そして、まるで親戚のおじさんへの愛着と親しみの情ゆえにそうなったかのような「イジリ」や「ツッコミ」まであって、読んでいるこちらまで楽しくなってくる評論です。
「おじさん、あらすじの説明をはじめる。それがまた、起きる出来事を漫然と並べただけの、実に退屈な説明。」
「本人もそう思ったらしく『こんな筋書きを書くのはいやになった』と、突然あらすじ放棄。」
「おじさん、話をあちこち飛ばすし、下手をすると『説明しなくちゃ』と言い訳しつつ、とうとう別の思い出話にかまけて説明なしに終わってしまう頁まである。」
もうこんな感じなのです。
しかし、サブカルチャー案内人の先駆者とでもいうべき存在である天下の「J・J」をつかまえて、「お笑いじゃないんだから」と思うようなほどおみごとな「イジリ」と「ツッコミ」です。
こんな評論、植草甚一について書かれたほかの書評ではなかなか読めないと思います。
恩田陸のそんな「単刀直入さ」に思わず笑ってしまいます。
しかしながら、読んでいるこちらも「こんな書き方あり?」とツッコミを入れたくなるほど、実際、いいかげんな箇所があることはあるのです。
恩田は、このように奇妙な記述になっているのは、一見読者に語りかけている文体だけれども、これが植草甚一による「自分のための覚書」だからと結論づけています。
なんとも奇妙な本。でも、いつ読んでも楽しい気分になれる本。
そういいながら、恩田は『雨降りだからミステリーでも勉強しよう』を評論していきます。
探す、読む、聴く、書く。雑学好きで軽やかな「J・J」への賛辞
『雨降りだからミステリーでも勉強しよう』は、恩田陸が書いたようなツッコミどころもあるのですが、なんといっても、「本探しの達人」ともいわれる植草甚一の本に対する ”目利き” が十分に発揮されている名著です。
当時、海外ミステリー小説は翻訳されていないものも圧倒的に多く、「J・J」は原書で読むことを至上の歓びとしていたようです。
「古本屋を回って、エドマンド・クリスピンやマイケル・イネスのペーパーバックを探すなんて羨ましい。」
恩田陸がこう書いているように、J・Jは「散歩と雑学好き」で有名なおじさんであり、その軽やかなフィールドワークで長年、街を歩き回り、本を探しまくって、ブックレビューを書いていました。
また、本に限らす、海外ジャズのレコード評を雑誌「スイング・ジャーナル」に寄せたり、ドアーズやピンク・フロイドなど、当時、最先端のロックバンドの素晴らしさを語って世に広めたりもしています。
そんなわけで、『雨降りだからミステリーでも勉強しよう』では、J・Jの”目利き”による、まだ翻訳もされていない当時最新の、日本ではまだ誰も知らないようなおもしろい海外ミステリー小説の数々が紹介されていたりします。
「今の私にこそ役に立つ情報も満載。イアン・フレミングやジョルジュ・シムノン
、四百冊以上も本を書いたジョン・クリーシーらの小説作法やアドバイスも、決して端折らず淡々と訳してくれている。」
と、恩田陸もJ・Jおじさんの現代でも通用する先見性のある ”目利き” が生きているこの本のすばらしさを絶賛します。
そう、1908年生まれのJ・Jおじさんは神保町の書店街などを歩き回って、コツコツと好きな本を探しまくってきて、40歳を過ぎてから評論を書き始めました。
そして、1960年後半から1970年代にかけて爆発するような勢いで注目された人です。
いま風に言うのなら突然「バズる」わけです。
植草甚一は常時好きな本を買いまくっているために、晩年になるまで裕福ではなかったと聞きます。彼の蔵書は4万冊にもおよんだということです。
いまでも年間300冊は本を読むというとんでもない読書家である恩田陸。
そんな彼女は、植草甚一の『雨降りだからミステリーでも勉強しよう』の書評を、なによりも最高の賛辞とも思えるこんな言葉で締めくくっています。
「「いやはや」おじさんの地図は広すぎる。大人になっても、小説家になっても、こんなに面白く読めてしまうし、またきっと読み返すだろうと思ってしまうのだから。」
恩田陸が言う「何度読んだか分からない」本。
ぜひ、そんなすばらしい本にめぐり逢いたいものですね。
「おもしろい本」が見つかる「読書法」【第4回】
ちまたにはさまざまなブックレビューであふれています。
そんななか存在する「作家が書いた書評集」。
プロフェッショナルが語る「本音」が読める貴重なものです。
心の奥に響く本音のレビューを読む「たのしみ」。
また、そこで取り上げられた本自体の「おもしろさ」。
それらには格別な味わいがあると感じています。
〈目次〉
恩田陸の『土曜日は灰色の馬』から松本清張について

三島由紀夫と松本清張の間には大きな「確執」があった?
前回は、恩田陸の書評集『土曜日は灰色の馬』から、三島由紀夫の小説への評論を紹介、解説しました。
今回はその三島由紀夫と大きな「確執」があったのではないかとも言われている作家・松本清張を取り上げたいと思います。
三島由紀夫は「松本清張の文学を認めない」という強固な発言をしたといわれます。
これは中央公論社が文学全集を刊行するに際して、作品のラインナップに松本清張のものを入れようとしたところ、編集委員のひとりだった三島由紀夫がこれに大反対したということなのです。
かたや官僚の子息として恵まれた環境に育ち、華やかに作家活動に入った三島。
かたや貧困家庭に育ち、尋常小学校を卒業するとすぐに就職し、その後、苦しい生活の中で失業すら経験。戦争に招集され従軍。戦後になってどん底から這い上がるようにして、雑誌の懸賞小説への応募をきっかけに大ベストセラー作家となった清張。
そもそも育った環境もその作風もまったく違っているふたりです。
真相は定かではありませんが、おたがいに、自分にない才能やバックグラウンドに嫉妬していたとか、三島はメキメキとベストセラー作家にのし上がってきた松本を脅威と感じていたとか、ちまたではさまざまに言われてきました。
三島のほうが過剰に清張を意識していたのではないかという話もあり、ライバルのような存在のふたりであったことは間違いないようです。
恩田陸が「昭和のアリバイを崩した男」と呼ぶ松本清張
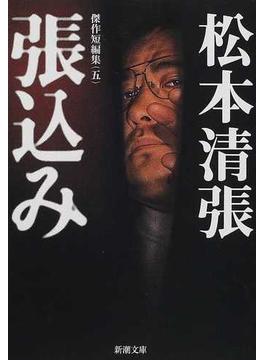
『点と線』『ゼロの焦点』『小説帝銀事件』『日本の黒い霧』『わるいやつら』『砂の器』『けものみち』『黒革の手帖』など、推理小説からドキュメンタリーまでその作品群は多岐のジャンルにわたります。
みなさんはきっと、小説を読んだり、映画やテレビドラマなどで一度は「松本清張作品」に触れているのではないでしょうか?
松本清張は、1976年に毎日新聞社による全国読書世論調査「好きな著者」の1位になると、それ以降、なんと8回も1位になったことがあるといいます。
それほど当時、売れっ子作家であった清張は、犯罪と戦後史が重なり合うようなプロットで作品を書く社会派の推理作家とも言われました。
政界と財界の癒着、官僚の腐敗などによる政治献金、国有地払い下げなど、戦後の疑獄事件といわれるような大きな社会的問題をベースに描かれた作品も多くあります。
ひとつの事件を追っていくと、それが実は別の社会的に大きな事件につながっていたというようなプロットを得意とした作風。
まさに画期的な作家が奔出したというような新たな発見と驚きともいうべきか。
それが推理小説における「清張以前、清張以後」という語り継がれる ”言葉” がレジェンダリーなものとして残っているゆえんでもあります。
現在でも年間300冊ほどの読書家である恩田陸は、本書『土曜日は灰色の馬』の中の「昭和のアリバイを崩した男 松本清張『張込み』」と題された書評で、
「戦後の復興期から高度成長期にかけて、『なかったこと』にされてきたものを、彼は次々と『実はあった』と証明していった。
貧困、病気、差別、格差、学歴社会、家族の亀裂、共同体の崩壊、などなど。それを、エンターテインメントという形で読者に示してみせたのだ。」
といいます。
かつて、作家の半藤一利(文藝春秋社編集部員として松本清張の担当を経験した)と文芸評論家の清原康正、書店・有隣堂社長の松信 裕の三者の対談において、
半藤は、
「もちろん小説もすごいのばかりでした。 しかも、小説としてすごいだけじゃなくて、裏側にそれぞれのテーマがはっきりあるんです。 当時の社会的な話題をパッとキャッチして、小説の中に取り込む。 それは驚きました。」
と語っています。
つまり、半藤はここで、逆に言えば、松本清張の小説の背景には社会的テーマがきっちりとあり、それを大衆的なエンターテインメントとしても十分に読ませることができる才能にあふれた作家だったという、恩田陸と同様のことを示唆しているのですね。
ニュータイプな作家・清張の偉業と、現代へ放たれる危機意識
松本清張と三島由紀夫は、それぞれ、社会への大きな問題意識、危機意識を持っていましたが、その質、ベクトル、作品への描き方には180度といってもいいくらい大きな違いがありました。
「社会への問題意識、危機意識」。どうしても社会的な存在とならざるを得ない「物書き」であれば誰もが持っている意識だとは思います。
「もはや、誰もが『降りて』しまった世界で、清張を読むというのはどこかノスタルジックな感慨を起こさせる」
恩田はそう語ります。
「誰もが『降りて』しまった世界」。
とてもクールで、残酷で、こわい言葉ですね。
「(松本清張の)『神々の乱心』は、事によると、オウムの先取りなんです。 ある一つの妙な新興宗教が宮中にいて、それがいろいろやるわけです。 ですから、あのテーマは、現代人はどういうものに魅せられているのかというものを、清張さんが感じたのかなと思うんです。
今の作家たちは、もう少し現代とまっすぐ向かえよと言いたくなるんです。 若い人たちがどうしてみんな自分たちのつまらない世界に潜り込んじゃうのか。」
最後に、恩田陸は、
「ギラギラと上を狙い、野心を持てあがく時代は過ぎ去ってしまった。若者でさえ、死に物狂いで働いておカネ持ちになるより、平凡で穏やかな生活を送りたい、と宣言してしまう時代である。」
「かといって、清張が暴いてきたものが消えたわけではない。むしろ、以前よりも見えにくい形で、貧困も格差も広がっている。この不在証明を骨太なエンターテインメントを、現在の我々は、まだ見つけられていないのだ。」
と、作家としての危機意識も漂わせるようなとても重い発言をもって、清張の評論を終わりとするのです。
松本清張。戦後昭和の大胆にして繊細な大作家。
しかも、推理作家というエンターテイナーにとどまらず、筋金入りのジャーナリスティックな作家活動を貫いた、稀有な作家であったと思います。
「おもしろい本」が見つかる「読書法」【第3回】
ちまたにはさまざまなブックレビューであふれています。
そんななか存在する「作家が書いた書評集」。
プロフェッショナルが語る「本音」が読める貴重なものです。
心の奥に響く本音のレビューを読む「たのしみ」。
また、そこで取り上げられた本自体の「おもしろさ」。
それらには格別な味わいがあると感じています。
〈目次〉
恩田陸の『土曜日は灰色の馬』から三島由紀夫について

昭和のエンターテイメント界に燦然と輝いた「スター 三島」

第2回で、恩田陸の傑作な書評集『土曜日は灰色の馬』から、小川洋子といっしょに川端康成について書かれた書評を取り上げました。
今回は、川端を父のように尊敬し、川端もとてもかわいがっていたといわれる三島由紀夫についての、とびっきりおもしろい書評がありますので紹介したいと思います。
書評のタイトルには「ケレンと様式美 スター 三島に酔いしれたい 三島由紀夫『春の雪』」とあります。
読み進めていくと、恩田陸は作家としての三島由紀夫がとても好きなことが強く伝わってきます。
何といっても、タイトルで「スター 三島」と言っているくらいですし。
もちろん三島は万人が認めるであろう日本文学界における「大スター」であります。
いや、世界的にといっても過言ではありませんね。
まずは、いきなり16歳の時に執筆したデビュー作『花ざかりの森』。
まるで鮮やかな「ショート・フィルム」集でも観ているような斬新な短編集で、「天才が現れた」と世の読者を驚かせます。
センセーショナルな登場のしかたもありましたが、当時、やはりそこに書かれたものから感じられる彼の作家としての高いポテンシャルに、誰もが圧倒されたはずです。
いまのプロ野球にたとえれば、「令和の怪物」と呼ばれる千葉ロッテ・マリーンズの若手投手、佐々木朗希の登場のようなものでしょうか !?
デビュー以来初の先発ローテーション入りした2022年4月10日、開幕間もない対オリックス・バッファローズ戦。
いきなり「13者連続奪三振」、「1試合19奪三振」(プロ野球タイ記録)、「プロ野球史上28年ぶりの完全試合達成」。
しかも「最年少記録更新」というおまけまでついた、あの強烈なインパクトのような・・・。
1回目に続いて、野球のたとえで恐縮です!
三島由紀夫の活動は文壇だけにとどまらず、多岐にわたります。
たとえば、映画では、俳優として、若尾文子、勝新太郎、石原裕次郎ら往年の名優と競演。映画『憂国』では原作はもちろんのこと、監督、主演までしています。
このように、三島由紀夫は間違いなく昭和の「大スター」という存在でした。
三島の小説は「舞台の上の芝居」 それをうっとりと鑑賞したい
さて、小川洋子と川端のふたりを論じた、どこか重く深刻な文章とは打って変わって、ここでの恩田陸の評論には、カラッと明るく元気で、どこか「小粋」な印象すら受けるのです。
恩田は、今や三島を語る人が「楯の会」の自決の話ばかりになってしまっていることには納得がいかないとし、
「あれじゃあ、ただの変な人で終わったみないじゃありませんか。
私が『一見上品なふりをしているが本当はスケベは世界文学』というテーマで密かに選定しているベストテンでも上位に入る、『憂国』みたいなエロいものもあるのに。」
なんてことも書いているのです。
ここで映画『憂国』の話が出ましたね。
「じゃあありませんか」という、これまでとはちょっと異質な、くだけた文体。
そして、『一見上品なふりをしているが本当はスケベな世界文学』なんていうテーマ。
そんな「恩田シェフ」ならではのユニークさ。あふれ出るユーモア。
ここはもう、思わず笑わずにはいられませんよ!
彼女はほんとうに大の三島由紀夫のファンのようですね。
この評論において、彼女は三島の小説を以下のようにたとえています。
「彼の小説は、舞台の上で演じられる芝居なのだ。
これを客席から素直にうっとり鑑賞し、決して書割りの後ろを覗いたり、緞帳をめくってみたりしないこと。
それが三島を楽しむコツだと私は信じている。」
「歌舞伎を見ても、なぜあんな変な化粧してるんだ、なんであんなところから出てくるんだ、なんであんな奇妙なポーズなんだとは追求しないはずである。
それと同じことが三島由紀夫にもいえる。」
たしかに、『潮騒』『金閣寺』『午後の曳航』『憂国』など、挙げていけばきりがないほど、三島由紀夫の小説には演劇的な要素が強くうかがえます。
それゆえか、多くの三島作品が映画化されています。
実際、三島は歌舞伎の台本『地獄変』を書き、『近代能楽集』、『サド侯爵夫人』、『鹿鳴館』などの「戯曲物」をたくさん書いています。
『近代能楽集』は三島が「能」を文字どおり近代劇に訳したもので、ニューヨークをはじめ海外でも上演されて、世界に「能」を知らしめました。
また、『サド侯爵夫人』は、日本での公演におとらず、海外でも大きな人気を集め、パリ、ロンドン、ストックホルム、ブリュッセルなど、世界各地で頻繁に上演されてきました。
このように、三島由紀夫は演劇的な要素に満ちあふれた小説家であり、実際に優れた舞台芸術作家でもありました。
スピリチュアル系の世界でも映えわたる三島の「芸」
恩田陸がここで取り上げた三島由紀夫の小説『春の雪』は、全4巻からなる小説『豊饒の海』の1巻目で、貴族の恋愛物語をテーマに描かれます。
三島最後の長編小説となった『豊饒の海』は、輪廻転生や仏教、神道、能など様々な要素が交じり合った幻想的な作品といわれています。
その内容は難解で、現在でもさまざまな解釈、さまざまな読まれ方をしているのです。
さて、この三島由紀夫の “最後にして最大の問題作” とも思える『豊饒の海』ですが、恩田は『豊饒の海』について、
「これは、平たく言うと輪廻転生の話なのだ。(中略)三島が完全にスピリチュアル系の世界に足を踏み入れた話なのである。」
と語ります。
過去にそちら側に行ってしまった作家の例はたくさんあるけれど、そんな時はいつも淋しい思いで本を閉じるという恩田陸。
「しかし、三島由紀夫の場合は平気だ。
彼の場合、本当に信じていたのかもしれないが、それすらも彼は演しもの(だしもの)として舞台の下から観ているからである。」
と、ここでも三島への絶大な支持が揺らぐことはありません。
三島の小説は、最後まで計算された絶妙なコントロール下にあった「舞台の上の芝居」だったということを言いたいのですね。
「スピリチュアル系」な書き物について、ここで恩田陸が言及している、あまりにも傑作なくだりがあるので、引用したいと思います。
「巷にはスピリチュアル系のものが溢れている。感動ストーリーや自己啓発のビジネス本にはかなりの確率でそういったものが含まれているのだ。」
といいます。
また、彼女はそうした類の本を否定はしないし、それらを求める気持ちがわからないでもないとしながら、
「けれど、その手の本の安易で安っぽい芸のなさには憎悪を抱いている。
こちとら、年中プロットに命を懸けているというのに、このスカスカなストーリー、似たような構成はどうにかならんものか。」
と、バッサリ!
はあ〜、ここで「こちとら」ときましたよ!
「恩田シェフ」というより、バリバリな江戸前の「板さん風情」といった感じでしょうか?
ここはもう、 「恩田板長」とも呼ぶべき、なんとも威勢のいい「包丁さばき」ではありませんか !?
いわゆる「べらんめえ口調」ってえやつでやんすかね?
本来の「作家・恩田陸」の立場に還って、この本の中でもほかにはない、高いテンション、熱を帯びて語られます。
「どうにかならんものか」と来るのですからね。
いやあ~、ほんとうにおもしろいですね、恩田陸!
そしてこの書、『土曜日は灰色の馬』は、やはり傑作!
彼女は、
「魔法の言葉」や「いくつかの習慣」で簡単に魂のステージを上がれるくらいなら、誰も苦労はせんわい。
せめて、『豊饒の海』くらいの芸がなきゃ。」
「ですから、『春の雪』はその手の本の芸ある見本としても読めます。」
とこの評論を締めています。
徹頭徹尾、三島由紀夫の礼賛ですね。
まあ、それも当然でしょう。
こんなにスケールの大きい不世出の文学界のエンターテイナー、そうはいないでしょう。
三島由紀夫最後の長編小説『豊饒の海』は『春の雪』『奔馬』『暁の寺』『天人五衰』の全4巻からなります。
とても長い小説ですが、まずはこの『春の雪』で「スター三島」の芸に酔いたいものです。
「おもしろい本」が見つかる「読書法」【第2回】
ちまたにはさまざまなブックレビューがあふれています。
そんななか存在する「作家が書いた書評集」。
プロフェッショナルが語る「本音」が読める貴重なものです。
心の奥に響く本音のレビューを読む「たのしみ」。
また、そこで取り上げられた本自体の「おもしろさ」。
それらには格別な味わいがあると感じています。
〈目次〉
恩田陸の『土曜日は灰色の』から小川洋子と川端康成について

恩田陸カラーが色濃く出ている「名刺代わり」の巻頭エッセイ
前回は、恩田陸が書いた『土曜日は灰色の馬』という書評集と、その著者である恩田陸に関するアウトラインを話したところで終わりました。
今回はその続きとして、いよいよ彼女の“痛快”な書評に接して、どんどん読むのが楽しくなる『土曜日は灰色の馬』の中身について、詳しく紹介、解説していこうと思います。
本書の冒頭には、著者の恩田陸による文庫本にして23ページほどの「ガラス越しにささやく」というタイトルのエッセイが配されています。(本書のための書き下ろしではありませんが)
長編小説のゲラ刷りの校正をするために、彼女が数日間ホテルに泊まり込みで作業しなければならないという時間的に追い詰められた状況に置かれます。そんな中、静謐な深夜、どこか古めかしく古典的スタイルのホテルの一室で彼女がさまざまなに空想をめぐらせるくだりから始まります。
ホラー作家の大家であるスティーヴン・キングの小説『シャイニング』ばりの、現実の世界からすこしずつズレていくような非日常的な浮遊感覚。どこか幻想的で「うすら寒い」恐怖を感じさせるような巧みな文章。いかにも恩田陸らしい色合い。
僕はそれほど熱心な彼女の小説のファンというわけではないのですが、恩田ファンが歓んでページをめくる姿が目に浮かぶような、まさに「ノスタルジーの魔術師」と呼ばれる彼女ならではの描写力が生きた味のあるエッセイです。
「深夜のホテルでの非日常的な空想」、「都会の町の風景の変遷」、「匂いに関する人間の感覚」、「写真という記録の不完全さ」、(彼女がしばしば小説のヒントになるとも言う)「雑踏から聞こえてくる会話や目の前を通り過ぎていく景色、昔から頭に浮かぶ現実に見たものなのかどうか確かでない不思議な情景」。
これら5つのテーマについて恩田陸の非凡な感性でエッセイは綴られていきます。
本書が「書評本」であることを踏まえれば、このエッセイは、彼女の小説を読んだことがない読者に向けた「私はふだんこんなことを、こんなふうに考えたり感じたりしている小説家なのです」という「名刺代わりの自己紹介」のようにも思えてくるのです。
「食材」が大作家でも手抜きなし 恩田シェフのスペシャルメニュー
さて、落語の「まくら」のように、本書の冒頭、短くも読者の気を惹くエッセイで、まずはサクッとそつなく楽しませる。さすがは現代の売れっ子エンターテイメント作家恩田陸です。
もちろん、これ以降が書評集『土曜日は灰色の馬』の本領が発揮される楽しみなページとなります。
「どんな料理を注文しても一皿一皿外れがなくて、注文するのに迷ってしまうような、まるで、人気メニューが盛り沢山なビストロのよう」
僕がこの本の読後に抱いたイメージです。
まあ、店はビストロでもフレンチ・レストランでも、割烹料理店でも、なんでもいいのですけれど。とにかく「恩田シェフ」がミシュラン級の「いい仕事」をビシッと決めてくれる「名店」であることは確かです。
本書は、
Ⅰ 面白い本はすべてエンタメ
Ⅱ 少女漫画と成長してきた
Ⅲ 暗がりにいる神様は見えない
という3章で構成されています。
ではまず「 Ⅰ 面白い本はすべてエンタメ」と題された、小説を中心とした書評の数々が詰まった最初の章から、これは恩田シェフの「スペシャルメニュー」だと思う極めつけの評論をいくつか紹介していきましょう。
小川洋子と川端康成は「猟奇作家」で「変態作家」!?

『猫を抱いて象と泳ぐ』(小川洋子著 文春文庫)
「深化する 小川洋子の小説」と題された書評では小川洋子と共に川端康成も俎上に。
恩田陸はここで、いきなり研ぎすまされた切れのいい包丁を思いっきり振るいます。
いわく、
「国民作家、川端康成は本質的には猟奇作家であり、大変態作家だった。」
とバッサリ!
大作家、川端康成をつかまえて彼女は強烈な言葉を吐くのです。
続けて、
「その幸福な上澄みである『雪国』や『古都』を愛する国民が、やはり本質的には猟奇作家であり変態作家である小川洋子(もちろん、誉め言葉である)の幸福な上澄みである『博士の愛した数式』を愛したのだと思うと、日本国民、なかなか侮れないものがある。」
と言うのです。
こうした忌憚のない評論に、「えっ、なんで?」と混乱する人たちと、逆に「やるなあ〜」「攻めてるね」と思わず唸る人たちもいると思います。
彼女が「すごい」と思うところはそこです。さすがはデキる評論者、恩田陸!
「猟奇作家」?
「大変態作家」?
老舗版元、筑摩書房から出版されている書評本に、いきなり、ノーベル文学賞受賞者、日本が世界に誇る作家、川端康成に向けたなんとも衝撃的な言葉が出てきものだと、思わず笑ってしまいそうなほどの強いインパクトですね。
しかし、川端康成の『眠れぬ美女』や『みずうみ』という小説を読んだことがある読者なら、この「猟奇作家」や「大変態作家」という表現にはそれほど抵抗もなく、驚きはしないかもしれません。
彼らは恩田陸に向けて「よくぞ言った!」「よくぞ書いた!」と快哉を叫ぶことでしょう。
『雪国』や『古都』で日本の伝統的な美を描いてノーベル文学賞を受賞した川端ですが、その後に書かれた小説はそこに留まることはありませんでした。
川端の後期の作品『眠れぬ美女』は " ロリコン小説 “ 、『みずうみ』は " ストーカー小説 “ などと称されることがあります。また、『山の音』という、老人が自分の息子の嫁にひそかな恋心を抱いて惑うなんていう、これまた危険な小説もあります。
学校で習う教科書に載っている『雪国』だけではない川端康成の奥深き世界。川端が後期に書いた退廃的な色合いの強い小説を読むことなしに、川端文学の正体を識ることは難しいかもしれません。
恩田陸は、川端の『雪国』、『古都』と小川洋子の『博士の愛した数式』を"幸福な上澄み"と表現します。
恩田陸の言う ”幸福な上澄み” とはどういうことでしょうか? ”上澄み” ということは、底に沈む ”澱り” のような、なにかどろどろしたものもあるということでしょうか・・・。
「猟奇」「変態」という部分は ”上澄み” ではない、底にある本質的なものということなのでしょうか?
彼女はさらに、
「『猫を抱いて象と泳ぐ』を書いた小川洋子は、小説というもの、あるいは自分の小説が幸福な上澄みとして読まれることをどこかきっぱりと拒絶したように思える。」
と続けます。
さて、これははたしてどんなことを意味しているのでしょうか?
チェスを愛する主人公の少年 ”リトル・アリョーヒン ”の数奇な人生を描いた小説『猫を抱いて象と泳ぐ』は2011年に発表された小川洋子の代表作とも呼び名の高い小説です。11歳で身体の成長を止めた主人公はチェス盤に無限の可能性を求めていきます。
ネタバレになってしまうので、これ以上の内容を書くことは避けますが、小川洋子の優しく、美しく、しかも現実を残酷なまでに描くという彼女の作風が貫かれた興味深い小説です。
ところで、川端の極めてエロティックでデカダンスな小説といわれる『眠れる美女』は、その作風から話題となり、発表当時、他の作家たちからもさまざまに評価されました。
『眠れる美女』はラテン・アメリカ文学の名手として『百年の孤独』や『予告された殺人の記録』などの著書で知られるコロンビア生まれのノーベル文学賞受賞作家ガルシア=マルケスにも影響を与えました。ちなみに、大江健三郎や中上健次らはマルケスの『百年の孤独』に大きな影響を受けているようです。
川端の『眠れる美女』にインスパイアされたマルケスは、後にエッセイ『眠れる美女の飛行』(1982年)や『わが悲しき娼婦たちの思い出』(2004年生)という本を書いています。
川端は1972年にガス自殺で亡くなります。享年72歳。どこまでが真実なのかはわかりませんが、その事情や原因について書かれているとして有名な『事故のてんまつ』という臼井吉見による本が1977年に出版されて、当時、大きな話題となりました。はたして、晩年の川端にはどんなことが起きていたのでしょうか?
恩田陸は、小川洋子の『ミーナの行進』という小説の中身に触れて、
「川端康成の自殺を受け、図書館で最初は『伊豆の踊り子』などを借りていた朋子が『眠れぬ美女』を借り出すところが、やけに意味深に感じられてくる。」
と、まさに「意味深に」この評論を結びます。なにか含むところが多く感じられる締め方ですよね。
作家の書いた書評を読んでみることで見つかる「おもしろい本」
紙幅にしてわずか2ページという短く簡潔な小川洋子と川端康成に関する評論。しかし、ふたりの文学者の核心を突くような切れ味の鋭さと中身の濃密さに驚かされます。
「猟奇作家」で「変態作家」の小川洋子、「猟奇作家」で「大変態作家」の川端康成。恩田陸がふたりをそう呼ぶ意味、その所以にはとても深いものがあるわけです。
この評論に興味を持った読者は、恩田陸がここで取り上げた小川洋子の『博士の愛した数式』『猫を抱いて象と泳ぐ』『ミーナの行進』の3冊と、川端康成の『雪国』『古都』『眠れる美女』の3冊、これらの作品に興味津々、読み比べたくなってくるのではないかと思います。
みなさんはいかがでしょうか?
ただ「なんとなくよさそう」といって本を選ぶのではなく、強い関心や興味を持ったという「理」があって本を手に取り読んでみるということが、より深い読書の「愉しみ」になるといえるでしょう。
「作家の書いた書評」を読んでみること。
それこそが「おもしろい本」が見つかる「読書法」ではないかと私は思うのです。
では、次回も恩田陸の書評集『土曜日は灰色の馬』の魅力について、さらに詳しく紹介、解説していきます。
どうかお楽しみに!
「おもしろい本」が見つかる「読書法」 【第1回】
ちまたにはさまざまなブックレビューがあふれています。
そんななか存在する「作家が書いた書評集」。
プロフェッショナルが語る「本音」が読める貴重なものです。
心の奥に響く本音のレビューを読む「たのしみ」。
また、そこで取り上げられた本自体の「おもしろさ」。
それらには格別な味わいがあると感じています。
〈目次〉
作家の書いた傑作「書評集」を読もう!

『土曜日は灰色の馬』(恩田 陸著 ちくま文庫)
依然として「本のチカラ」は大きい 「1冊の本」から得られること
インターネットが隆盛の現代社会においてもなお、「1冊の本」から得られることには、質・量ともに大きなものがあると思われます。
たとえば、昔からよく聞く話に、「大きな会社のトップになるほどたいへんな読書家で、年に数十冊もの本を読んでいる社長も多い」というのがあります。
これは日本に限らないことで、IT事業で世界的革命を起こし、巨額の富を築いたビル・ゲイツやイーロン・マスクも「超」がつくほどの読書家として有名です。
現代社会は、インターネットの普及により、だれもが手軽にスマホやパソコンで検索すれば、さまざま情報を簡単に、瞬時に知ることができます。
「まだインターネットがなかった頃は、こんな調べ物はどうしていたのだろう?」と思うくらいに、今では知りたいこと、わからないことがあると、すぐにインターネットで調べるのがあたり前のこととなりました。
しかし、インターネットで得られる情報は、「1冊の本」に詰まった情報のたしかさ、大きさ、深さには到底かなわないという側面があります。
お金を払って買う(有料で書店に並ぶ)本にはやはりそれなりの「たしかな価値」というものがあるのです。
ということで2022年末には、ずばり、先に挙げたふたりにアマゾンのCEO ジェフ・ベゾスを加えた3人の『天才読書 世界一の富を築いたマスク、ベゾス、ゲイツが選ぶ100冊』 (日経BP )なんていう、贅沢というか、なんともすごい本も出版されました。
この大御所3人が取り上げる本のジャンルは、経営、リーダー論から、経済学、科学、歴史、国家論、生き方、小説、ノンフィクションなどに至るまで多岐に渡っています。
彼らは子供時から大の読書家だったとのことです。しかも、その後も起業してから現在至るまでの間、さまざまな分野の本をむさぼるように読むことで、事業のアイデアの源泉としたり、今でも本からさまざまな分野の先端の知識や情報をインプットしているのです。
現代のIT業界の寵児である彼ら3人ともが「たいへんな読書家」であるという、なにかパラドックス的ともいえるこの逸話は、現代でもすぐれた本に学ぶことが大きく人を成長させる象徴的なケースとしてみることができるでしょう。
プロフェッショナルの「眼力」は、はるかに高い「境地」を識る
話は本から離れますが、現在、野球評論家をしている落合博満という人がいます。彼は打者として日本のプロ野球史上唯一の3度の「三冠王」になっています。
それだけではなく、落合は現役引退後には監督として後進の選手を指導にあたり、それなりの成績も残しています。
打者としていわば前人未踏の頂点を3度も極めた落合が、いま現在、評論家としてプロ野球界の選手に向ける目。その審美眼には非凡なものがあります。
2018年5月、落合が日本のプロ野球チーム「日本ハムファイターズ」から大リーグの野球チーム「エンゼルス」に移籍したばかりの大谷翔平に関して、
「エンゼルスにはプホルスっていう3,000本打つバッターがいる。彼、DHなのよ。このDHをわざわざ守らせてまででも大谷を欲しいと言った時点で、大谷の存在は我々が考えている以上に米国では大成功」
「日本で二刀流がいいとか悪いじゃなくて、もう米国でも認めたの。こんな強いものはない。最初からこれは成功なの」
と、大方の予想をはるかに上回る大谷翔平の今日までの大活躍をまるで見据えたかのように、この時点で大谷にすでに高い評価を与えているのです。
落合にこうした先見の明があったからこそ、現在も彼の野球評論が注目を浴びていて、テレビ局のスポーツニュース番組などの解説者、コメンテイターとして引っ張りだこになっているのだと思われます。(これとは対照的に、同じく元プロ野球選野球評論家の張本勲には、過去に、大谷翔平の「二刀流」に関しても、「大リーグ行き」に関しても否定的な発言がみられました)
プロフェッショナルの秀でた「眼力」。これはもちろん、野球界における落合満博の例だけではありませんね。
NHKのテレビ番組『プロフェッショナル 仕事の流儀』ではありませんが、たとえば、あなたが思いつくままに、各界、あるいは自分の関心のあるジャンルにおける「プロフェッショナル」な人のことを思い浮かべるとしましょう。
そんな時、おそらくあなたはきっと、その人の秀でた手腕の秘訣を、彼の本心や関心事を知りたいと思うのではないでしょうか。そしてそれらを自分に取り入れてみたり、参考にしたいと思うことでしょう。
また、プロフェッショナルな人物に関して、たとえばこんなふうに思うことはないでしょうか。ちょっと例を挙げてみます。
〇ビートルズのジョン・レノンがリスペクトしていたミュージシャンや楽曲って、どんな人、どんな曲があっただろう?
〇大リーガー・大谷翔平の目にいま目標として見えている野球の先人はいるのだろうか? いるとしたらそれは誰なのだろう?
〇将棋の藤井聡太五段が目指す棋士とは? 将来のライバルは、もしや人間を超えた「AI棋士」か?
スポーツ、音楽、料理などなど、ジャンルはなんであれ、専門家としてその道を究めたプロフェッショナルには、なにがどのように見えているのか。
経験の深さと高いスキル、そして鋭い審美眼。そこから生まれる理論は、凡人にはなかなかたどり着けない「境地」に達するような興味深いものとなるに違いありません。
作家が書いた「本についての本」を読むという読書の「愉しみ」
先に述べたビル・ゲイツ、イーロン・マスク、ジェフ・ベゾスら3人の巨匠がどんな本を読んできたのかを知り、それらをむさぼり読んでみるのもいいでしょう。
“元祖文春砲”とでもいうか、『文藝春秋』に掲載した記事がきっかけとなって元内閣総理大臣の田中角栄を逮捕に追い込んだと言われ、また「知の巨人」とも呼ばれた伝説のルポライター・立花隆(故人)。その著書『ぼくはこんな本を読んできた 立花式読書論、読書術、書斎論 』(文春文庫)には、立花が自身の「血肉」となったものとして、たくさんの本を紹介しています。これらの本を片っ端から読んでみるのもまたいいことでしょう。
それらとすこし意味合いは違いますが、「高校生の時に読むべき〇冊」とか「二十歳になったら読むべき〇冊」など、読書週間などに、いわゆる「良書」がリストアップされたものもなどもよく見ます。
しかし、このようにして挙げられた本をなかば学問するように、学習するかのように読むこととは別に、もうすこし純粋に「読書」を楽しむとしたら、まず読んでみるといいと僕が思う「特殊な本」があります。
それが小説家が書いた「本についての本」。つまり、「小説家が書いた書評集」なのです。
そこには先に書いたように、その道を究めた「プロフェッショナル」な人の視点から見た本に対する評論、評価」がぎっしりと詰まっています。
作家が書いた書評集を読むことをすすめるのは、それらを読むことによって、「本のプロフェッショナル」による究極の「本の評価」や「本の読み方」、そして「本の楽しみ方」を知ることができるからなのです。
新聞や雑誌に載るような書評や紹介文とはひと味もふた味も違う、作家が本音で語る本に対する評価、評論に出会うことができます。プロフェッショナルならではの「すごみ」にあふれた「判定(ジャッジ)」と言えるでしょう。
そんな貴重な「本音」に触れ、その本質を知り、味わうこと。
まさにこれこそが作家が書く「本についての本」を読むという愉しみ、醍醐味にほかならないと思うのです。
そしてまた、その本に対する作家の評価と、自分の評価とを比べることで、自分がその本のエッセンスをどこまで深く、どれほどしっかり読み込めているかを知る、ひとつのバロメーターにもなりうると言えます。
恩田陸が書いた “痛快“ な書評集『土曜日は灰色の馬』
作家が書いたすばらしい書評集はたくさんありますが、今回、僕がここでまず最初に取り上げたい本は恩田陸の『土曜日は灰色の馬』(ちくま文庫)です。
本書は2006年から2010年にかけて作者の恩田陸が晶文社のホームぺージに掲載したエッセイを主体に、そこに書籍の解説などを集めて編纂された書評集。
恩田陸といえば1992年に『六番目の小夜子』で作家デビューすると、SF、ミステリー、青春小説など、幅広いジャンルの作品を次々と執筆。2004年には、80キロを夜通し歩く高校生活最後の行事「歩行祭」を舞台に青春群像を描いた『夜のピクニック』で吉川英治文学新人賞、本屋大賞を受賞しています。
2006年、17名もの死者を出した不可解な大量毒殺事件の真相が次第に明らかになっていくという小説『ユージニア』で日本推理作家協会賞を受賞。2016年には国際ピアノコンクールに挑む4人の若者の姿を描いた小説『蜜蜂と遠雷』で、直木賞と本屋大賞を受賞。本書は2019年に女優の松岡茉優を主演として映画化もされています。
恩田陸は、読む者をどこか郷愁に誘うような美しい、そしてせつなくさせるような情景描写を得意としていて、そのため「ノスタルジアの魔術師」とも称されています。
また、幼いころから読書好きで、現在も「年間300冊読む」というとてつもない読書家であることに驚かされます。
彼女が書いたこの書評集は、根っから本を愛し、「ものがたり」に造詣の深い作家である彼女ならではの、取り上げる本への心からの賞賛があり、あるいは時に忌憚のない辛辣な評価があり、毒気もあり、SF作品も手がける作家ならではの空想、ファンタジーなど、さまざまな要素を巧みに織り交ぜながら丹念に綴られています。
まさに、現代を代表するエンターテインメント作家らしい、読む者を引きずり込むようなその文章、描写力に、「書評集」ということも忘れて、小説さながら思わず引きずり込まれてしまう魅力、いや「魔力」と言えるようなものさえ感じさせます。
そんな彼女の『土曜日は灰色の馬』という書評集が持つ最大の魅力。それは、俎上に載せる本がたとえ大作家の筆による著名なものであろうが、まったく遠慮することなく自身の感想を自由に述べ、彼女ならではの「スパっ」と切れのいい評価、判定(ジャッジ)をしっかりと下しているところなのです。
では、次回は恩田陸の『土曜日は灰色の馬』のその中身、おもしろさや魅力について詳しく紹介、解説していくことにします。お楽しみに!

2019年に公開された恩田陸原作の映画『蜜蜂と遠雷』予告編動画