「おもしろい本」が見つかる「読書法」【第4回】
ちまたにはさまざまなブックレビューであふれています。
そんななか存在する「作家が書いた書評集」。
プロフェッショナルが語る「本音」が読める貴重なものです。
心の奥に響く本音のレビューを読む「たのしみ」。
また、そこで取り上げられた本自体の「おもしろさ」。
それらには格別な味わいがあると感じています。
〈目次〉
恩田陸の『土曜日は灰色の馬』から松本清張について

三島由紀夫と松本清張の間には大きな「確執」があった?
前回は、恩田陸の書評集『土曜日は灰色の馬』から、三島由紀夫の小説への評論を紹介、解説しました。
今回はその三島由紀夫と大きな「確執」があったのではないかとも言われている作家・松本清張を取り上げたいと思います。
三島由紀夫は「松本清張の文学を認めない」という強固な発言をしたといわれます。
これは中央公論社が文学全集を刊行するに際して、作品のラインナップに松本清張のものを入れようとしたところ、編集委員のひとりだった三島由紀夫がこれに大反対したということなのです。
かたや官僚の子息として恵まれた環境に育ち、華やかに作家活動に入った三島。
かたや貧困家庭に育ち、尋常小学校を卒業するとすぐに就職し、その後、苦しい生活の中で失業すら経験。戦争に招集され従軍。戦後になってどん底から這い上がるようにして、雑誌の懸賞小説への応募をきっかけに大ベストセラー作家となった清張。
そもそも育った環境もその作風もまったく違っているふたりです。
真相は定かではありませんが、おたがいに、自分にない才能やバックグラウンドに嫉妬していたとか、三島はメキメキとベストセラー作家にのし上がってきた松本を脅威と感じていたとか、ちまたではさまざまに言われてきました。
三島のほうが過剰に清張を意識していたのではないかという話もあり、ライバルのような存在のふたりであったことは間違いないようです。
恩田陸が「昭和のアリバイを崩した男」と呼ぶ松本清張
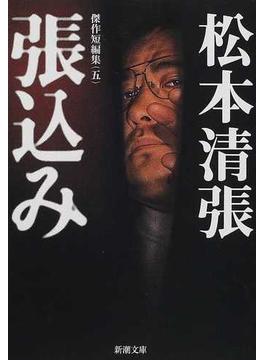
『点と線』『ゼロの焦点』『小説帝銀事件』『日本の黒い霧』『わるいやつら』『砂の器』『けものみち』『黒革の手帖』など、推理小説からドキュメンタリーまでその作品群は多岐のジャンルにわたります。
みなさんはきっと、小説を読んだり、映画やテレビドラマなどで一度は「松本清張作品」に触れているのではないでしょうか?
松本清張は、1976年に毎日新聞社による全国読書世論調査「好きな著者」の1位になると、それ以降、なんと8回も1位になったことがあるといいます。
それほど当時、売れっ子作家であった清張は、犯罪と戦後史が重なり合うようなプロットで作品を書く社会派の推理作家とも言われました。
政界と財界の癒着、官僚の腐敗などによる政治献金、国有地払い下げなど、戦後の疑獄事件といわれるような大きな社会的問題をベースに描かれた作品も多くあります。
ひとつの事件を追っていくと、それが実は別の社会的に大きな事件につながっていたというようなプロットを得意とした作風。
まさに画期的な作家が奔出したというような新たな発見と驚きともいうべきか。
それが推理小説における「清張以前、清張以後」という語り継がれる ”言葉” がレジェンダリーなものとして残っているゆえんでもあります。
現在でも年間300冊ほどの読書家である恩田陸は、本書『土曜日は灰色の馬』の中の「昭和のアリバイを崩した男 松本清張『張込み』」と題された書評で、
「戦後の復興期から高度成長期にかけて、『なかったこと』にされてきたものを、彼は次々と『実はあった』と証明していった。
貧困、病気、差別、格差、学歴社会、家族の亀裂、共同体の崩壊、などなど。それを、エンターテインメントという形で読者に示してみせたのだ。」
といいます。
かつて、作家の半藤一利(文藝春秋社編集部員として松本清張の担当を経験した)と文芸評論家の清原康正、書店・有隣堂社長の松信 裕の三者の対談において、
半藤は、
「もちろん小説もすごいのばかりでした。 しかも、小説としてすごいだけじゃなくて、裏側にそれぞれのテーマがはっきりあるんです。 当時の社会的な話題をパッとキャッチして、小説の中に取り込む。 それは驚きました。」
と語っています。
つまり、半藤はここで、逆に言えば、松本清張の小説の背景には社会的テーマがきっちりとあり、それを大衆的なエンターテインメントとしても十分に読ませることができる才能にあふれた作家だったという、恩田陸と同様のことを示唆しているのですね。
ニュータイプな作家・清張の偉業と、現代へ放たれる危機意識
松本清張と三島由紀夫は、それぞれ、社会への大きな問題意識、危機意識を持っていましたが、その質、ベクトル、作品への描き方には180度といってもいいくらい大きな違いがありました。
「社会への問題意識、危機意識」。どうしても社会的な存在とならざるを得ない「物書き」であれば誰もが持っている意識だとは思います。
「もはや、誰もが『降りて』しまった世界で、清張を読むというのはどこかノスタルジックな感慨を起こさせる」
恩田はそう語ります。
「誰もが『降りて』しまった世界」。
とてもクールで、残酷で、こわい言葉ですね。
「(松本清張の)『神々の乱心』は、事によると、オウムの先取りなんです。 ある一つの妙な新興宗教が宮中にいて、それがいろいろやるわけです。 ですから、あのテーマは、現代人はどういうものに魅せられているのかというものを、清張さんが感じたのかなと思うんです。
今の作家たちは、もう少し現代とまっすぐ向かえよと言いたくなるんです。 若い人たちがどうしてみんな自分たちのつまらない世界に潜り込んじゃうのか。」
最後に、恩田陸は、
「ギラギラと上を狙い、野心を持てあがく時代は過ぎ去ってしまった。若者でさえ、死に物狂いで働いておカネ持ちになるより、平凡で穏やかな生活を送りたい、と宣言してしまう時代である。」
「かといって、清張が暴いてきたものが消えたわけではない。むしろ、以前よりも見えにくい形で、貧困も格差も広がっている。この不在証明を骨太なエンターテインメントを、現在の我々は、まだ見つけられていないのだ。」
と、作家としての危機意識も漂わせるようなとても重い発言をもって、清張の評論を終わりとするのです。
松本清張。戦後昭和の大胆にして繊細な大作家。
しかも、推理作家というエンターテイナーにとどまらず、筋金入りのジャーナリスティックな作家活動を貫いた、稀有な作家であったと思います。